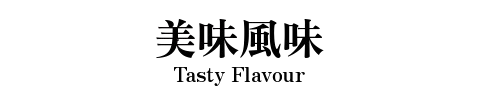カリウムは多めに、ナトリウムは控えめに
食事や健康の話になると、よく「塩分を控えましょう」と言われますよね。でも、同じくらい大切なのが「カリウム」と「ナトリウム」のバランスです。本稿では、カリウムとナトリウムの働きやその理想的なバランス、そしてその考えを日々の食事にどう活かせるのかを、科学的な視点からわかりやすく解説します。
カリウムとナトリウムの役割
カリウムは、体液の浸透圧を決定する重要な因子です。また、酸・塩基平衡を維持する作用があり、神経や筋肉の興奮伝導にも関与しています。ナトリウムは、胆汁、膵液、腸液などの材料です。
現代人の食事は「ナトリウム過多・カリウム不足」
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、ナトリウム(食塩相当量)は、男性で7.5g未満、女性は6.5g未満、カリウムは、成人男性3.0g以上、女性2.6g以上が目標とされています。ナトリウムは摂りすぎる人が多いので上限が設定されていますが、カリウムは摂りすぎても問題ないとして、上限の目標値は設定されていません。
うまくバランスをとれると、血圧が下がる
ナトリウムの摂取量を1とした時、カリウムの摂取量を、およそ1.5~2とすることが、WHOなど医療機関では推奨されています。カリウムは、ナトリウムを体外に排出する助けをする役割を果たしているため、カリウムを摂取することによって、ナトリウム摂りすぎによる血圧の上昇が回避できることがわかっています。
マクロビオティック的な理想比率
体液の中の比率に合わせる
マクロビオティックをはじめとした自然療法やホリスティック医療の分野では「体液の中のカリウムとナトリウムの比率は5対1に近い」とされ、それに倣う形で「食事でも5対1が理想」とする説が見られます。
カリウムが多い食材とナトリウムを控える味付け
カリウムが多い食材、すなわち、ほうれん草、かぼちゃ、アボカドといった野菜類、豆類、果物、いも類を使用しましょう。ナトリウムを控えるためには、だしや香味野菜、酢で味付けることで塩を控える、加工食品を避けて自炊する、ことがポイントとなります。
つまり、陰陽のバランスをとるということ
既に説明している通り、マクロビオティックでは体内でのバランスを重視します。ナトリウムを多く含む動物性食品は陽性、カリウムを多く含む植物性食品は、より陰性と分類されます。詳しくは「陰と陽の話」というページをご覧ください。
まとめ
「5対1」という比率を厳密に守るのは現実的ではありませんが、カリウムを意識して増やし、ナトリウム(塩分)を少しずつ減らしていくことで、体にやさしいバランスを実現することができます。カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に取り入れ、減塩の工夫をするだけでも効果は大きいです。まずは、ちょっと意識することから始めてみましょう。健康的な食事は、数字よりも「日々の積み重ね」です。気負わず、できることから取り組んでいきましょう。
参考文献
からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て
日本人の食事摂取基準(2020年版)
※本ページにはアフィリエイトリンクを含みます。リンクを経由して商品を購入すると、筆者に紹介料が入ることがあります。